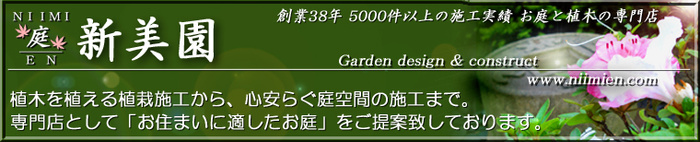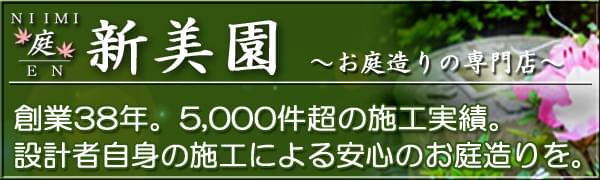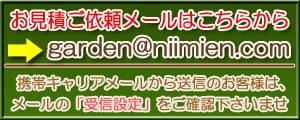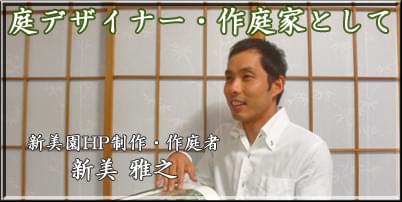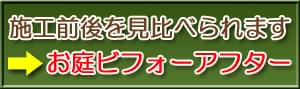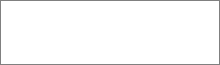今回ご相談をいただきましたA様邸の玄関はとても広く、大理石の床も明るく開放的な空間でしたが、階段下にあたる角部がデッドスペースになっている点でお悩みになられていました。

坪庭施工前の様子
そこでこの階段下のスペースを有効活用するべく、ご帰宅時に和風坪庭が出迎える様なデザインをご提案させていただく事になりました。
課題としては上部に階段が走っている事で人工植物に高さ制限がある事、坪庭となる向こう側には別室の大窓がある為、向こう側からも眺めて成り立つ様な表裏デザインが求められる事、等が挙げられました。
今回はこの課題をデザインへ活かしつつ、和の風情が凝縮された様な坪庭をお造りする事になりました。

玄関から眺める室内坪庭
玄関の中に設えた坪庭の全景です。
まず植物については全て人工物のフェイクグリーンであり、当然に水やり等は不要です。
しかし人工黒竹については幹と枝が本物の竹に防腐加工が施された製品である為、ディテール自体は本物の竹と全く同じというクオリティを得られています。
灯籠や手水鉢、庭石といった石類は屋外造園で扱う本物を使用しておりますので、屋外造園と変わらない品質で坪庭を表現する事が出来ます。
レイアウトとのテーマしては、手水鉢を起点とする枯れ流れを岬灯篭が照らしている、という構図となっています。
まず灯篭・手水鉢・枯れ流れという3つの景観ポイントを三角形で結ぶ事で景観の基礎とし、重心となる庭石の配置も三角形を結ぶようなラインでレイアウトしています。
これにより全ての材が一直線に並んでいる事が無くなり、坪庭をどこから眺めても前後左右の位置変化による遠近感を感じる事が出来る様になります。

小さな坪庭の中で感じる立体感
玄武岩の黒色が美しいピンコロ石で囲った坪庭は、三角構図によりどんな角度からも立体感や奥行感のある眺めを楽しむ事が出来ます。
例えば正面からのアングルよりも、この様な斜めからのアングルの方が日常的に眺める事の多いものであり、何かの手前に必ず何かがあり、一番奥にも何かがある、といった様な3段階の奥行が坪庭に奥深さを添えています。
手前に見える鳥海石は幅60cmクラスの大型ですが、石質上手持ちで搬入する事ができる上、重量も人よりかなり軽いという点で床への負荷の問題も生じません。
岬灯篭と知足型手水鉢は甲州鞍馬石の台石に乗せられており、実際よりも大きく見せ、離れた場所からも目に入りやすくなる様になっています。

坪庭の上部空間を最大限に活かす
玄関ドアが開いて外からの光が入れば、まるで屋外の坪庭であるかの様な瑞々しさを感じられます。
設計時において坪庭内で活用できる上限高さを計測しており、それぞれのポイントに適合する高さの人工黒竹をレイアウトしています。
屋外であれば低く感じる1.5mと1.2mといった製品規格ですが、室内に持ち込めば相応に立派な竹に見え、階段下の空間を最大限に有効活用する事が出来ております。
尚、この人工黒竹は3本が台座に固定されている製品ですが、1.2m規格のものは台座ごと3分割に分解し、1本ずつ間隔を空けて自然の竹に近いレイアウトを行っています。
これにより黒竹は石材を包み込む様なレイアウトはもちろん、傾きや方向性を取り入れた表現も行う事が出来ます。

庭石や石材を引き立てる苔の表現
室内造園のにおける大きなメリットとして、苔をふんだんにレイアウト出来るという点が挙げられます。
屋外造園で天然の苔庭を構成すれば相応のメンテナンスが必要となり、そもそも苔の生育に適している環境であるかどうかも求められます。
それに対し室内造園の苔は全くメンテナンスを必要としない為、自由な苔ラインを取り入れて設計を行う事が出来ます。
ドライモスについてはハイゴケを乾燥着色したものであり、繊細な手作業によってひとつまみずつ坪庭へレイアウトしていきます。
石類に自然に付着した様な苔は粉物を付着させて表現しており、この苔の付き方も日向日陰をきちんと設定した上で屋外であれば苔生すであろう位置を決めてレイアウトしています。

反対側から眺める坪庭は日陰の趣を表現
設計時の課題でありました反対側からの眺めは、日陰の坪庭の様にしっとりとした雰囲気を感じられる様にデザインしています。
植物が多く見え、苔の膨らみ方も大きく、苔が石に上って増えていく様な表現も取り入れています。
暗く見えるアングルなら暗い場所に生きる植物の状態を表現し、明るい場所は開放的にデザインを優先させる、室内であっても自然に習った景観を行う事でよりリアルな坪庭になるのではないでしょうか。
お気付きになられる方もいらっしゃるかと思いますが、この場所は底が床面であるのに庭石が地面に埋まって据え付けてある様に見えるのも大切なポイントです。
これは庭石選びの段階で平面に近い面を持つ石を多数探し、その面を床側にした場合に良い趣を見せてくれる石のみを事前に全て決めて搬入しています。
つまり室内造園の場合はどの石がどの位置に設置されるかが完全に決まっており、これによりきちんと半分土に埋められたかの様な自然な庭石に見えるという事になります。
今回の室内坪庭は奥行きも感じられデザインも繊細でありますが、実際の面積は幅1.9m×奥行1.2m程の小さなスペース上にデザインしております。
実際はこの半分ほどの面積であっても室内坪庭をデザインする事は可能でありますので、もしご自宅のデッドスペースの活用にお悩みになられている方がいらっしゃいましたら、是非お声掛けをいただければと思います。